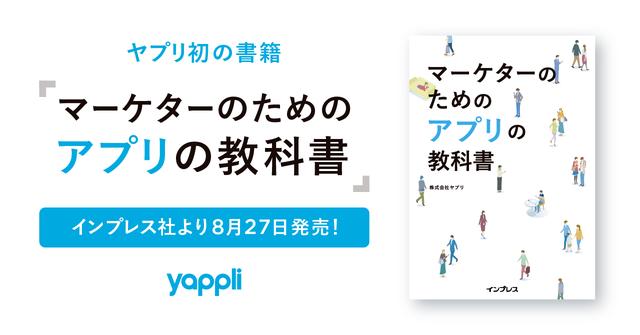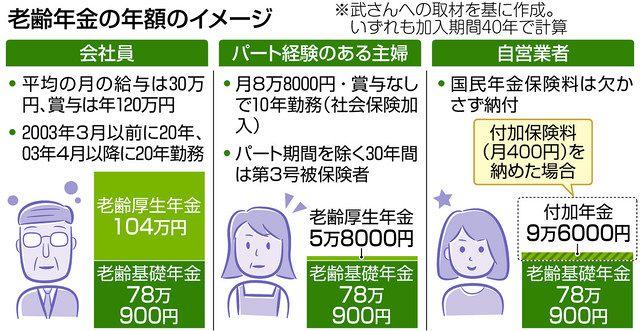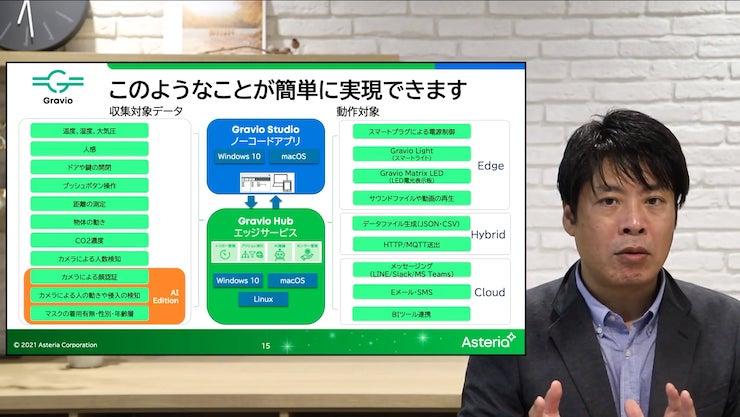40年近く前に、大きなブームとなり社会現象を巻き起こした家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」の開発責任者、上村雅之さんが亡くなりました。78歳でした。
2019年の春、京都放送局に勤務していたゲーム好きの筆者は上村さんにインタビューする機会を頂き、最後にこんな質問を投げかけました。
「上村さん、いつまでも飽きないゲームって、できると思いますか?」
その答えは、コロナ禍のいまだからこそ、胸に響きます。
おととし上村さんに行ったインタビューの内容を元に記事を書きました。
“ファミコン”の衝撃
家庭用ゲーム機のファミリーコンピュータ。通称「ファミコン」。1983年6月、バブル前夜の日本で発売されました。えんじ色のボディーに、長方形のコントローラー。この見た目に、懐かしさを覚える人も思います。世界での累計販売台数は6000万台。大人も巻き込んだ社会現象になりました。そのファミコンの開発にあたって、京都のゲーム会社「任天堂」で開発責任者を務めていたのが、上村雅之さんです。原動力になったのは、「自分が遊んでみたい」という純粋な気持ちだったといいます。ゲームは全部、大人が遊びたいがためにつくったものです。面白くしたいという目的が明確ですからね。遊びたいという思いを映像などで表現してお金に換えることができたのが、ゲーム業界だと思います。社会現象の影で
子どもたちがブラウン管のテレビを取り囲み、お茶の間の風景を一変させたファミコン。上村さんにとっても予想外の売れ行きだったといいます。上村さんは、その理由について、コンピューターの処理能力の向上やゲームの魅力を伝えるメディアの発達、子どもたちを取り巻く環境の変化など、さまざまな条件がちょうど組み合わさったのではないかと分析しています。ゲームなどの高級玩具は、都市部でよく売れるんですが、都市部から外れると、意外と昔ながらの遊びもされている。つまり、都会では外で遊ぶのがなかなか難しくなる時代に差しかかってきたところに、家での遊びとしてビデオゲーム機が出てきたのではないかと一方、ゲームに熱中する子どもたちが続出し、依存症やひきこもりなどを心配する親や教育関係者からの批判も多かったといいます。しかし、上村さんはむしろ、外遊びが難しい時代に、ゲームが子どもたちを結びつける大事な役割を担っていたのではないかと考えました。テレビゲームに対する批判のなかに、テレビに向かって一人で遊んでいる姿がいかにも孤独だという批判がされていたんですが、どうも現実は逆のようでした。一緒にゲームの画面を見ることで人の遊び方を研究して、次に自分の番が回ってきたらトライする。ゲームを必死に遊んで、攻略情報を電話でやりとりする。ゲームが人と人との接着剤になっていて、それがファミコンの大きな魅力のひとつだったと思います海外でも大ヒット!秘密は“キャラクター”
「日本人ほど、キャラクターを作るのが上手で好きな人たちはいない」そう語る上村さんは、ファミコンが海外でも大ヒットした理由のひとつとして、日本人が生み出すキャラクターの魅力があったと考えています。日本ではものに命が宿るという考えがあります。アニミズムですね。しかも、それを商品にしてきた歴史が本当に古い。海外の暴力的なゲームに対して、日本では平和なアニミズムの世界がゲームでも再現されています。キャラクターがゲームの中心になったので、ルールは簡単です。“パックマン”は鬼ごっこだし、“ポケットモンスター”は、いわば虫取り。世界中の誰でも遊びが理解できるから、コミュニケーションツールとしての機能も非常に高かったと思いますゲーム研究者として第2の人生を歩む
上村さんは、ゲーム開発者から研究者へと転身、日本で唯一のゲームを専門とする学術機関、立命館大学ゲーム研究センターの立ち上げにかかわり、初代センター長を10年にわたって務めました。このセンター、ゲームファンにはたまらない、あるプロジェクトを運営しています。 “ゲームアーカイブプロジェクト”です。国内で発売されたあらゆるビデオゲームのソフトや攻略本、ゲーム雑誌などを収集しています。ただのコレクションしているわけではなく、れっきとした研究の一環です。ゲームを文化財として捉え、これまで整備されてこなかった目録を作成して研究の環境を整えようとしています。ゲームや遊びの歴史を研究テーマに掲げる上村さんは、ゲームを保存する重要性をこう語りました。遊びというのは非常に根が深くて、技術的な面も含めて、いろんな文化要素の影響を受けています。ビデオゲームはその最たるものです。もしゲームをきちっと後世に伝えることができたら、100年前にこんなことをして遊んでいたということが、いままでと違う形で伝えることができます。グラフィックだけならアニメや映画でも可能ですが、遊び方そのものまで一緒に残せるわけですからゲームにフロンティアはあるか
ファミコンの誕生から38年。日本のゲーム産業は世界をリードするまでに成長しました。他人とコミュニケーションしながら遊べる「オンラインゲーム」や、VR=仮想現実の登場など、ゲームは目覚ましい進化を遂げています。では、ゲームに残された「フロンティア」は何なのか。上村さんは意外にも、ゲームはまだ「メンコ」を超えられていないと語りました。グラフィックという面では行き着くところまで来たということは否定できません。残るは入力、コントローラーです。開発者のとき、部下に”メンコの醍醐味をビデオゲームで出してよ”ってよく言っていたんです。メンコは地面にあるものを別のメンコで叩いてひっくり返します。そのビジュアルを表現することはできますが、叩くという感触をいまのコントローラーでは再現できない。色んなチャレンジがされていますが、まだ正解は見つかっていませんコンピューターの発達とともにゲームのグラフィックは年々進化を遂げ、現実と区別がつかないほどリアルな描写ができるようになってきています。しかし、最近、ファミコンのような「ドット画」が見直されているといいます。あまりにグラフィックを高度にすると、ゲームだと感じてもらえなくなる場合もあります。いまはむしろ、自分が想像する余地があるグラフィックが好まれている。ドット画には人の想像力をかきたてるものがあります。見えているのはリアルではないけど、頭の中にはリアルがある。想像する余地があるほうが、自分はこう見たとか、ああ見たとかを友達と共有する楽しさもありますこれからの遊びとは
これから、未来の遊びはどう変わっていくのか。上村さんが考える遊びとは何なのか。そのヒントも聞くことが出来ました。飽きないゲーム、飽きない遊びは存在しません。“人生は遊びだ”という有名な言葉があります。僕も75歳まで生きてみて、色んなことに夢中になって、どれもこれもが遊びだったなと思います。飽きてまた違うことをやっている飽きない遊びはないからこそ、人は新たな遊びを求め続けるのかもしれません。では、飽きないゲームを作ることはできないのか。最後にそう尋ねると、笑顔でこう答えてくれました。それは無理ですよ。やっぱり最終的に飽きないのは人間ではないですか「パックマンは鬼ごっこ、ポケットモンスターは虫取り」。「ゲームは人と人をつなぐもの」。「キャラクターが、ものに命が宿る世界の中で暮らす」。当時、上村さんから聞いた言葉を改めて思い返してみると、去年、コロナ禍で他人とのコミュニケーションが難しくなった時代に大ヒットした、「あつまれ どうぶつの森」が、頭に浮かびます。この2年、ゲームはさらなる進化を遂げ、“おひとりさま”でも楽しめるサービスはますます充実してきました。しかし、上村さんが語った「結局、最終的に飽きないのは人間」という言葉を、これほど実感した日々はありません。私たちはいつか、メンコを超えるゲームで遊ぶことができるのでしょうか。その日まで、ゲームに飽きてはまた新しいゲームに取りかかる日々を、飽きずに繰り返したいと思います。ご意見・情報をお寄せください